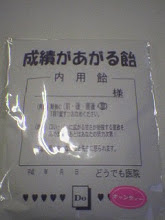マッチョ&角刈り「どうも〜。あ、書肆侃侃房から出た句集をいただきました、こんなんなんぼあってもええですからね」
— sorori (@sorori6) May 7, 2021
マッチョ「オカンがな、好きな句集を忘れたっていうねん」
角刈り「大丈夫かいな。ほんなら一緒に考えてあげるわ。どんな句集なん」
マッチョ「今年4月に出たばっかりの句集やって」
木田智美さんはな、口語俳句が魅力なんやから。«春光にさらして角砂糖かわいい»«あした穴を出ようと思う熊であった»なんて文語では表現できへん句や。あの神野紗希さんが句集に帯文寄せるほど、口語俳句の期待の星やで」
— sorori (@sorori6) May 7, 2021
マッチョ「タルトの句が有名やっていうねん」
角刈り「木田智美さんやないか!→
並べるようなお笑い好きやねんから。«春満月そのした京都アニメーション»なんて句もあるけど、基本的に社会とちょっとずれた日常詠が魅力や」
— sorori (@sorori6) May 7, 2021
マッチョ「オトンはな、俵万智ちゃうかって」
角刈り「歌人やないか!もうええわ」
というわけで、木田智美第一句集『パーティは明日にして』書肆侃侃房より