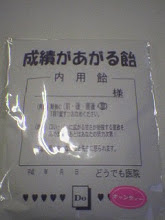田島健一さんが最近、Youtubeで短い動画をアップして、俳句に対する考えを発信している。(秘密の俳句ちゃんねる)
いろいろ面白いこと、興味深い発言が多く、刺激がある。
そのなかで、新しい季語は定着するか、という話があったので、関連づけて私見をまとめておく。
先に結論じみたことを言ってしまうと、私は新季語の創案、提唱に関して大推進派で、講座や教室でも奨励している。実際に定着する季語は少ないかもしれないが、試みとしては大いに進めればよいし、そもそも歴史的に季語は増え続けているのだから、今後も新しい季語はどんどん生まれると確信する。
また、新季語について考え、議論することで季語に対する考えが深まると思っている。
ありふれた事例でいえば、もちろん「スキー」や「スケート」、「ラグビー」などのスポーツ語彙はことごとく近現代のものであり、「扇風機」「ストーブ」などの家電、「キャベツ」「ブロッコリー」などの飲食物、「クリスマス」などの行事、など、どう考えても明治以降季語は増え続けている。
新しいのに気づきにくい季語もある。たとえば、「春一番」という季語は多くの俳人が好んで使うが、季語としては新しいものである。
このことは私も何度か書いており(季節のエッセー(29))、国語辞典編集者のコラムでも、1965年発表の小説や、1956年刊行の高橋浩一郎『日本の気象』(毎日新聞社)が古い例として指摘されている(日本語、どうでしょう 第251回「春一番」)。
同じくジャパンナレッジで提供されている季語エッセイでは、同じ春の強風をあらわす言葉として「春疾風」「春荒」「春嵐」などをあげ、季語としての定着は新しいと指摘している。
俳句のほうで中村草田男(「春疾風乙女の訪ふ声吹きさらはれ」)や石田波郷(「春疾風屍は敢て出でゆくも」)などが詠んでから、季語として注目され出し、普及した。
このエッセイでは、「春一番」の意味を、次のように解説している。
春一番という語感には、厳しく寒い冬から開放され、暖かい春の到来を期待させるいかにも明るい感じがあるが、実態はやや異なる。そもそもこのことばのルーツには、悲惨な海難事故がある。安政六(1859)年、旧暦二月十三日、長崎県五島沖に出漁した壱岐の郷ノ浦の漁師53人は、春先の強い突風にあって遭難、全員、水死してしまう。このとき以来、春の初めの強い南風を「春一(はるいち)」または「春一番」と呼ぶようになり、当地では今日でも二月十三日には出漁をみあわせ、「春一番供養」を行っている。......春北風も黒北風も一般的な冬の季節風のように長続きしないが、濃霧をともなうので、漁船にはたいへん恐い存在なのである。
こうした「明るい感じ」の源泉は、実はあの有名なアイドル曲らしい。
昭和51年(1976年)3月にリリースされたアイドルグループ・キャンディーズの9枚目のシングル「春一番」は大ヒットしました。作詞・作曲は穂口雄右(1948~)。195-60年代に広まった言葉を作詞家が取り入れて、1976年にヒットしたアイドル曲のイメージが、「春一番」という季語を支えている。
「雪がとけて川になって流れ、風が吹いて暖かさを運んできた」という歌のイメージは、当初の海難を引き起こす危険なイメージの「春一番」とは別の側面ですが、「春一番」という言葉を浸透させました。
そして、気象庁には「春一番」の問い合わせが殺到するようになり、気象庁は春一番の定義を決め、昭和26年(1951年)まで遡って春一番が吹いた日を特定し、平年値を作り、「春一番の情報」を発表せざるをえなくなっています。
新季語の利用についてしばしば言及されるのが、黛まどか氏の『月刊ヘップバーン』がかつて提唱した新季語だ。
ヘップバーン新歳時記には、現代の暮らしの中に新しく登場し、浸透してきた風物詩が提案されています。新季語は例句も少なく、どのように詠んだらいいのか、初心者でなくとも苦しむところです。......まずは、季語を自分で見たり聞いたり体験してみることが大切です。「ボージョレ」、「ポトフ」など飲食に関するものや、「新色」、「保湿」、「ブーツ」といったメイクや装いに関するものなら、比較的簡単に試すことができますし、「クリオネ」、「ホエールウォッチング」など、実際に目にすることが難しいものも、インターネット・書物・新聞・テレビなどから情報を得ることが出来ます。